まずは、その色彩感覚である。冒頭第一行を読んでいただこう。
空はすみれ色だった。星は緑色だった。そして太陽もまた緑色だった。
呆気にとられたのではないだろうか?
舞台は、アステロイドベルトの中の、小惑星パラス。ここと、同じく小惑星クィッコーが、ほぼ舞台の全てで、登場人物(生物)も、パラス人とクィッコー人のみ。このエイリアンの形態が、またなんというか。
いやいや、順序として、パラスの形状の説明からである。
パラス星は外側からこれを見ると樽形に見える。樽は天辺から底までが高さ40マイル、中心の横幅は30マイルである。そして樽の蓋にあたるところでは、上下とも円形蓋の面の直径は20マイルある。しかし、この樽に蓋は見あたらない。樽の内部には、上下とも深さ20マイルの中味の虚ろな漏斗が二つはまっている。二つの漏斗は先端同士が中心点で接合している。この中心点には孔が開いていて、これはいちばん狭くなったところでもなお半マイルの幅がある。この孔を通じて、二つの漏斗は相互に連絡しあう。がっしりと胴のふくらんだ樽は、ゆっくりと自身のまわりを−−中心点を横切って上から下へと通じている垂直線に沿って自転する。そして中味の虚ろな両漏斗を別とすれば、樽は堅牢な材質から成り立っている。
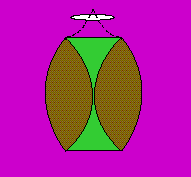
図を見ていただこう。(樽の上部の搭のような構造物と、雲のようなものについては、後述する。)私は初読の際、このページを読みながら図面を書いていたのだが、その奇抜過ぎる形状に納得がいかず、何度も読みなおしては書きなおしたことを思い出す。どうして、これほどまでに突飛な姿の星である必要があるのか。(ちなみに、重力の方向は、基本的には壁面に向いているが、事実上不定である。)
そして、登場人物たちの形態であるが、これもまた実に幻想的なものである。レザベンディオは吸盤脚を大きくひろげ、険しく切り立ったぎざぎざの岩壁にからみつけると、もとはといえばゴム状の円筒に吸盤をつけただけのその躯ごと、すみれ色の大気の中へと50メートルあまりも突兀とそそり立った。
レザベンディオの頭部は虚空でいちじるしい変化を遂げた。ゴム状の頭皮はいっぱいにひろげた雨傘のようにひろがり、それからゆっくりとすぼまった。すると顔が見えなくなった。こうして頭皮は前方に穴のあいた一本の円筒をかたちづくったが、この円筒の底には顔があって、その両眼から二本の長い望遠鏡のような仕掛けがせりあがり、レザンベディオはこれを使って、空の緑色の星々を、まるで手にとるように目のあたりに眺めることができるのだった。
これだけでも相当わけが判らないが、実態はこれどころではなく、パラス人の形態の記述は、物語の進行と共に執拗に繰り返され、その度に自在に変形する。いちいち引用しないが、どう考えても矛盾する描写も少なくなく、結局、ほとんど不定形なのではないかと思われる。作者は、局面ごとに必要な形態を(脈絡を無視して)とらせているかのごとくである。そのフォルムは、時には驚くべきものであって、発表年代(1913)を考慮すると、シュルレアリスムに影響を与えたのではないかとすら、思われる。
パラス星には、事実上、政府が存在しない。“指導者”と呼ばれるエリートたちはいるのだが、集団指導体制というよりは、集団無指導体制である。指導者たちは、ひとりひとりが芸術家であり、このパラス星を、自らの流派の様式で装飾する、または改造することに、余念が無い。建築家や彫刻家の他に、哲学者や鉱山発掘者、植物栽培者などもいる。
主人公は、レザベンディオ(略称、レザ)。彼は空想的建築家であり、パラス星の北部(図では上部)に、巨大な塔を建造することを夢見ている。彼のオブセッションは“二重星”への固執である。“二重性”といってもいいのだが、図示したように、パラスの北部上空には、光り輝く“雲”のようなものがある。彼は、この“雲”のさらに上部に、パラスと一体になって補完すべき、二重星のかたわれがあり、それがパラスの“頭部構造”なのだと考えている。図示した塔状の形態は、その頭部構造に到達するために建造されるべく、レザベンディオによって夢想されたものである。また、この(頭部構造への到達を阻んでいる)雲は、(期せずして日本語の洒落になってしまって申しわけないが)“蜘蛛の巣”状の物質であるということも、判っている。
この雲は、縺れも結び目もなく縦横に張りめぐらされた、数億兆の精巧な蜘蛛の巣繊維で作られていた。
“頭部構造”に対するレザベンディオの執着は、おいおい明らかになるのだが、とにかく、この、パラスの環境を激変させかねない大工事に着手するための、そして着手して以降は遂行するための、政治的駆け引きと、技術的ブレイクスルーの数々が、語られていくのである。
粗筋の細部を追うことは無意味なので、主要なモチーフを拾っていくことにしよう。
老パラス人、ピィパ。かれはレザベンディオの朋友であり、“二重星”に執着するレザに対して、“太陽”に執着する。
レザとピィパが別の小惑星、クィッコーに漂着し、そこから帰還するというエピソードがさしはさまれるが、そこで発見され、二人に同行してパラスにやってきたクィッコー人(いわば球形の小人で、これもまた形容に窮するような形態の、愛敬のある連中)は、塔の建設に重要な役割を果たす。
パラス人の“誕生”について。パラス人は、鉛鉱脈の中で発見される“胡桃”の殻を割ると、その中から誕生するのである。塔の建設のための労働力を確保するために、おおわらわで大量の殻を割り続けるという、一場面もある。誕生したパラス人たちは、生まれたときから大人である。そのひとりはポムピムパと名付けられる。
パラス人の“死”について。パラス人は、ある意味で“不死”である。自らが存在し続けることに、疲れと倦みを感じた時、パラス人は、別のパラス人に“吸収”してもらうのである。無論、存在も意識も消滅するが、吸収されたものの“性質”や“特性”は、吸収したものに引き継がれるのである。
レザベンディオの塔は、当初は高さ100マイルが必要とされ、それは長径40マイルのパラス星を破壊しかねないほどの大建築であるということもあって、ほとんどパラス人たちの支持を得られなかったのだが、やがて10マイルで十分だということがわかり、全星あげての大事業として取り組まれることになった。
図示した形状、及び、作品の発表年代から、勘のいい方は既に気付かれていようが、これは明らかに、エッフェル塔の比喩である。工事の進行状況の描写も、現実のエッフェル塔のそれと、極めて良く似ている(らしい)。
指導者たちのうち、芸術派の何人かは、単なる実用建築である塔に絶望し、レザベンディオに吸収されていく。このあたりも、エッフェル塔の是非をめぐって起こった議論を反映しているようである。
やがて“蜘蛛の巣”の正体が明らかになる。それは小さな頭をつけた、無数の生物の群生であった。80年も前のSFかと目を疑うほど、現代的な箇所である。
大建築の描写が延々と続き、ついに、塔は“蜘蛛の巣”に到達し、レザベンディオは“昇天”するために塔に登る。
このあとは−−要約が難しい。決して難解ではないが、コンセプトとビジョンが整理されていないように思えるのだ。全25章のそれぞれの冒頭で、各章の内容が要約されているのだが、最後の5章について、それらをそのまま引用する。
レザベンディオは塔上の孤独な部屋に籠って、きたるべき事態にそなえる。彼はついに一切の恐怖を鎮め、たとえいかなる事態が到来しようと、すべてがもはや恐るるに足りない−−完全な破滅すら恐るるには足りない、と思う。
次いで全パラス人が声を殺して見守るうちに、次の朝最後の階が建立される。光り雲に一大変化が起る。それはついに真ん中で張り裂けて、黄色い光の蛇行体が現われ、そのなかにレザベンディオが姿を没していく。
レザベンディオがパラスの頭部構造のなかで感じたことが述べられる。最初は何も聞こえず、何も見えないが、やがてまったく新しい視覚器官を得ると、これによって全遊星構造並びにとりわけ太陽がこれまでとはすっかり別物に見える。レザは未曾有の陶酔を感じ、最後に、太陽を全能と考えているものの声を−−そして遊星がなぜ太陽の周囲を回転するかという消息を耳にする。とこうするうちに、下のパラスの胴部で起った事件が記述される。
ゾファンティ音楽がばったり途絶える。そして上の最上階では、頭部構造の光線が塔の燈室と連結する。レザはなおも星たちの内部と星たちの望んでいることどもについて観察する。深紅色の光の球がパラス星中を横切る。続いてクィッコー星がパラスの月になる。レザはピィパに連絡をつけようとする。パラス人たちはパラス胴部の外側にばかり住むようになり、クィッコー人たちの協力の下に、大望遠鏡を建造する。頭部構造が巨大な彗星光芒を発光させ、また蜘蛛の巣がかつてのように煌々と照り映える。
ピィパは太陽観測のために、パラス胴部の外側の部分を中心部で張り包む新しいベルト道路を一基建設させる。レザはピィパに太陽に関するきわめて重要な問題を話す。ポムピムパが、レザ同様、頭部構造に入り込もうとするが、これは失敗に終る。彼はラプゥに引き取られる。クィッコー人たちがふたたびパラスに芸術性を要求する。パラスではしかるに、猫も杓子も天体観測に没頭中である。二つの隕石の精がパラスの近傍にきて、塔構造と頭部構造のまわりを旋回するが、排斥性の大気圏があるために近づくことができない。頭部構造は次第に低空に降りてきて、胴部と完全に密着してしまう。レザの青緑色の光がいまや下では一再ならず−−ときには多くの場所で同時に−−見られる。
蜘蛛の巣雲はついに一個の均斉のとれた環形構造へと整形され、ピィパはこの現象が典型的なものだと説明する。レザはピィパに、パラス人たちが塔建設の際に耐えた苦悩を思い起させ、パラス人たちに大いなる苦痛状態を告知する。パラスの頭部構造と胴部構造がついに接合するとき、その苦痛状態はやってくる。レザはこのとき最大の苦痛に耐えなくてはならない。全パラスがおそろしく震憾し、ついにいくつかのベルト道路さえ張り裂けて、巨塔が軋りはじめる。このあとレザは、自身が二重星と唯一不可分の存在になったと感じる。彼にとっての新しい生がはじまり−−あらゆるものが近づき合って−−小遊星環の星たちもまたたがいに接合し合う。
……なんとも、とらえどころのない、壮大なエンディングではある..
この年代(1913)の、タイトルが「小遊星物語」(原題は「Lesabendio:Ein Asteroidenroman」)という作品と来れば、普通誰でも、他愛の無い、古風な異世界漫遊譚だと思うだろう。しかしその実体は、全く異なる。これはほとんど、異常な物語である。
これは“過剰な”小説である。
エイリアンしか登場しないのはいいとして、彼らの、ほとんど必然性の感じられない、漫画的な形態。そして宇宙漫遊どころか、舞台は、ほぼひとつの小惑星上に限定され、そこにおける土木作業と政治的駆け引きの記述が、延々と続く。そして終盤になって現われる、恒星生命、宇宙生命という概念。超越的存在との合一。
エッフェル塔の建設をめぐる技術的驚異と、これをめぐる“芸術派”たちの闘い(とその敗北)の比喩を描きたいのであれば、舞台設定を間違えている。いうまでもないことだが、寓話は“変数”をひとつにすべきである。
一方、“超越的存在との合体”“宇宙的超生命の誕生”という概念を書きたいのであれば、この巨塔の建設の描写は長すぎる。ストーリーをシンプルで判りやすいものにしないと、こういう“超越的”テーマが引き立たない。
幻想的な舞台(ここまで述べなかったが、奇怪な形状のパラスに張り巡らされたベルト状の“高速道路”や、さまざまなイルミネーションの描写など、実に出色なのである)や、エイリアンたちの、やはり幻想的で変幻自在の形態を歌いあげたいのであれば、物語もテーマも、かっ飛び過ぎている。
さらに、これは最も現代的なSF、“ビッグプロジェクト(あるいは超巨大建築)テーマのSF”でもあるのだ。
“死”、“生命”、“芸術対技術”、等など、このさして長くもない小説に盛り込まれたアイデアと思想は、枚挙にいとまが無く、この過剰なテーマの収拾に失敗して、半ば支離滅裂な終り方をしていることすら、(皮肉ではなく)現代的である。
巨大なるものへの憧れ、超越的存在に吸収され、合一することへの憧れを、臆面もなく歌い上げているこの小説は、深読みすればまさに底無しである。“普通の部分”が全くない、例えて言えば、スポンジがない、クリームとデコレーションだけのケーキのようなこの小説を、しかし私は愛する。
 「小遊星物語」パウル・シェーアバルト 種村季弘訳 (平凡社ライブラリー)
「小遊星物語」パウル・シェーアバルト 種村季弘訳 (平凡社ライブラリー)(文中、引用は本書より)
 内宇宙への扉の入り口へ
内宇宙への扉の入り口へ 倉田わたるのミクロコスモスへの扉
倉田わたるのミクロコスモスへの扉
Last Updated: Feb 28 1996
Copyright (C) 1996 倉田わたる Mail [KurataWataru@gmail.com] Home [http://www.kurata-wataru.com/]